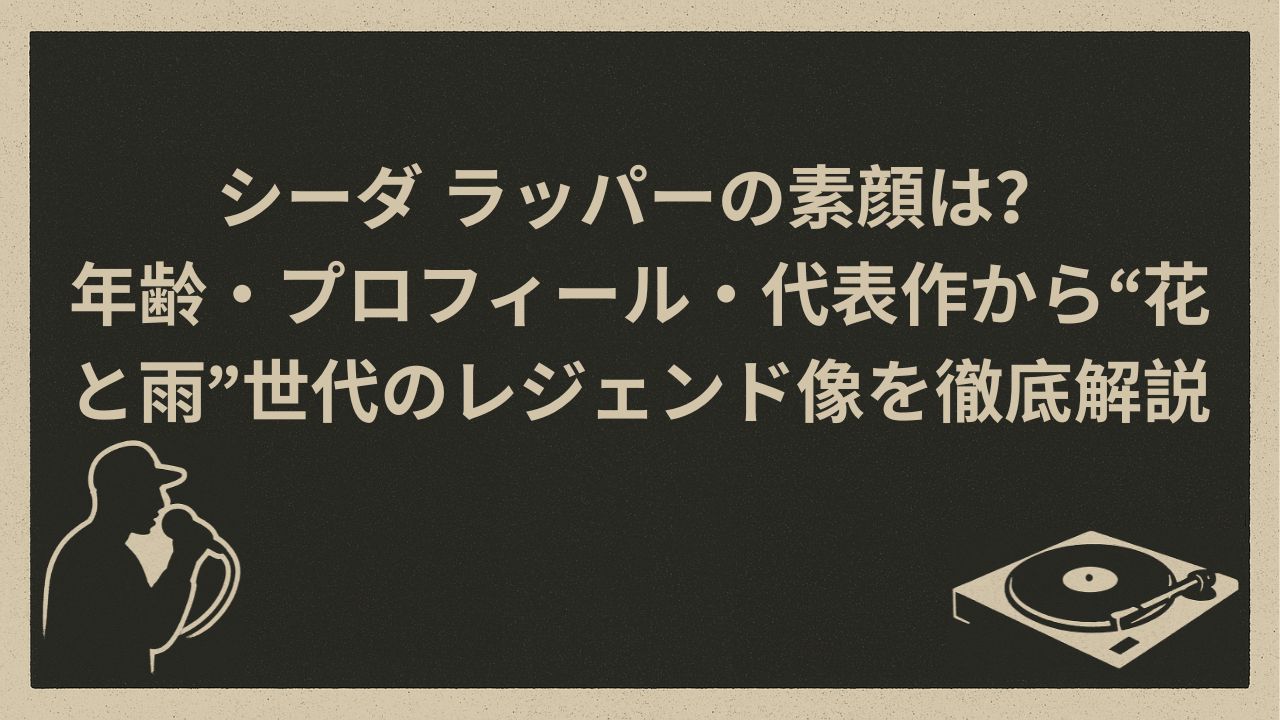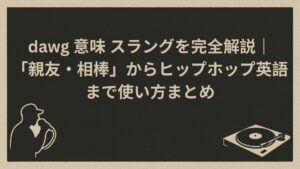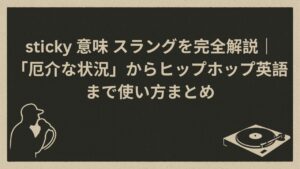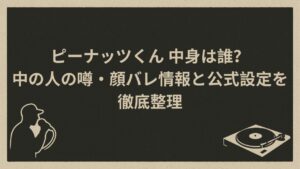シーダ ラッパーSEEDAの基本プロフィール|年齢・本名・身長・学歴まとめ

年齢・本名・MCネームの基本情報
まずは、シーダ ラッパー=SEEDAのいちばん気になる基本プロフィールから整理しておきます。
SEEDA(シーダ)は1980年11月17日生まれの日本人ラッパーで、2025年時点では40代半ばの年齢だと紹介されています。pucho henza+1
本名は「吉田なおひと」と記載されることが多く、MCネームは苗字の“YOSHIDA”を崩して「SHIDA」→「SEEDA」と変化してきたと言われています。pucho henza+1
「シーダってどう読むの?」と迷う方もいますが、読み方はカタカナで“シーダ”。
日本語ラップの文脈では、90年代後半から活動しているベテランラッパーのひとりとして語られることが多いですよね。ウィキペディア
出身地・身長・育った環境
シーダ ラッパーの出身地は東京都練馬区とされていて、プロフィール記事やWikipediaでも共通してこの表記になっています。pucho henza+1
一方で育った環境はかなり特殊で、3〜4歳頃から小学生〜中学生の一部をニュージーランドやイギリス(ロンドン)で過ごした帰国子女だと紹介されています。ウィキペディア+1
このため英語が堪能で、初期は英語多めのバイリンガルラップをしていた、というエピソードもよく語られています。bit-corleone.com+1
身長については「164cm」あるいは「推定164cm」と書かれている記事が多く、160cm台半ばの小柄なラッパーというイメージで語られることが多いようです。pucho henza+1
ライブ映像だけ見るとそこまで小さくは感じない、という声もあり、ファッションや立ち振る舞いで“サイズ感”をあまり感じさせないタイプだと捉えられている印象もありますね。
学歴とヒップホップとの出会い
学歴についても、シーダ ラッパーは少しおもしろい経歴を持っています。
ネット上のインタビューまとめやプロフィールでは、「高校は慶應義塾高校に進学したものの中退し、その後、神奈川大学に進学して卒業した」と説明されています。日本語ラップまとめ+1
高校〜大学時代にヒップホップと本格的に出会い、1996年頃から遊びの延長でラップを始めたと言われています。pucho henza+1
この大学時代に出会った人物のひとりが、後に『CONCRETE GREEN』シリーズでタッグを組むDJ ISSOで、日本語ラップシーンの流れを変えた重要なコンビだと評価されることもあります。ウィキペディア+1
こうしてまとめてみると、
- 1980年生まれ・40代半ばのベテラン
- 東京生まれだが、幼少期を海外で過ごしたバイリンガル
- 慶應→神奈川大学というバックボーンを持つストリート出身ラッパー
というのが、シーダ ラッパーSEEDAの基本プロフィールとして押さえておきたいポイントになりそうです。
♯シーダラッパー
♯SEEDAプロフィール
♯日本語ラップ
♯バイリンガルMC
♯神奈川大学出身
シーダ ラッパーの生い立ちとラップを始めたきっかけ

海外で過ごした幼少期〜帰国後の青春時代
シーダ ラッパーことSEEDAは、東京で生まれたあと、かなり早い段階から海外生活を経験していると言われています。
プロフィールでは「東京都で生まれ、3歳ごろから中学1年まで海外で過ごした」とまとめられていて、ニュージーランドやロンドンで幼少期〜小学校時代を過ごしたという紹介もあります。
英語圏で育ったこともあり、子どもの頃から自然と英語に触れる環境だったそうです。
のちのバイリンガルなラップスタイルや、英語フロウの滑らかさは、この時期の経験が大きく影響していると語られることが多いですね。
その後、日本に戻ってからは東京・神奈川エリアで学生生活を送り、高校〜大学時代にストリートカルチャーやヒップホップと本格的に出会っていきます。
「普通の日本の育ち」とは少し違うバックグラウンドを持っていたからこそ、シーダ ラッパーならではの視点や感覚が、後のリリックにも色濃く反映されていると言われています。
遊びの一環から始まったラップとManeuva時代
では、シーダ ラッパーが実際にマイクを握り始めたのはいつ頃なのでしょうか。
Wikipediaやインタビューのまとめでは、1996年頃、まだ10代半ばのタイミングで「遊びの一環としてラップを始めた」と書かれています。
当時はManeuva(マニューバ)というラップグループに所属しており、ライブ活動はしていたものの、メインMCではなかったとされています。
Red Bullのインタビューでは、グループのメンバーEguoとの出会いが大きなきっかけになったと語っていて、「もし彼がいなかったらラッパーSEEDAは生まれていなかったかもしれない」というニュアンスの話も紹介されています。
最初は“ガチでプロを目指す”というより、仲間内の遊びから少しずつステージに立つようになった、という流れだったようです。
それでも、19歳でSHIDA名義の1stアルバム『デトネイター』をリリースするまで一気に駆け上がっているので、「遊びの延長」とはいえ、当時からラップへののめり込み方は相当だったと考えられます。
シーダ ラッパーの生い立ちを振り返ると、
- 東京生まれ・海外育ちという少し特別なバックボーン
- 10代での仲間との出会いから自然に始まったラップ
- Maneuva時代を経て、“遊び”が本気のキャリアに変わっていったプロセス
といったポイントが見えてきます。
このストーリーを頭に入れておくと、初期作から最新作まで、SEEDAの作品の聴こえ方もまた少し変わってくるかもしれませんね。
引用元:https://pucho-henza.com/seeda-profile/
引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/SEEDA
参照元:https://ameblo.jp/matomero2011/entry-11129991815.html
参照元:https://www.redbull.com/jp-ja/rasen-08-seeda
♯シーダラッパー
♯SEEDA生い立ち
♯ラップを始めたきっかけ
♯海外育ちバイリンガルMC
♯日本語ラッププロフィール
シーダ ラッパーの音楽性とラップスタイル|名盤「花と雨」以降の変化

初期〜「花と雨」前:英語多めのバイリンガル&高速フロウ
シーダ ラッパーを語るうえで欠かせないのが、「花と雨」より前と後でハッキリスタイルが分かれると言われている点です。
初期のSEEDAは、かすれた声で文字数をギュッと詰め込んだ高速フロウが持ち味で、英語の比率がかなり高いバイリンガルラップの先駆け的存在として紹介されています。
歌詞の内容も、荒っぽいストリートライフやハスリングをダイレクトに描いたものが多く、「前期SEEDA=ハードでダークな世界観」というイメージを持つリスナーも少なくないようです。
日本語ラップがまだ“日本語か英語か”で揺れていた時代に、英語と日本語を行き来するスタイルで勝負していたところが、シーダ ラッパーの大きな特徴だと語られています。
このころの楽曲をまとめて聴くと、「世界で戦いたい」という野心や、コンプレックスと向き合うようなエネルギーが強く感じられる、という見方もあるようですね。
名盤「花と雨」で起きたスタイルチェンジ
そんなシーダ ラッパーのターニングポイントが、名盤として語られる4thアルバム「花と雨」です。
音楽メディアやファンブログでは、「花と雨」あたりから日本語のリリックが増え、フロウもゆっくり目になり、スタイルチェンジが起きたと分析されています。
英語多め・高速フロウだった初期と比べると、ビートの隙間をしっかり使いながら、ひとつひとつの言葉を噛みしめるようなラップに変わってきた、という指摘もあります。
同時に、重くブラックなだけだった世界観から、“喪失”“家族”“迷いながらも前に進む気持ち”といった感情が繊細に描かれるようになり、「泣ける日本語ラップ」として語られることも増えたと言われています。
プロデューサーBACHLOGICの叙情的なトラックと相まって、「花と雨」は日本語ラップ全体の歴史の中でも特別な作品だと評価されており、のちに映画化までされたことからも、その影響力の大きさがうかがえます。
その後のSEEDA:ポップさと深さのバランスへ
「花と雨」以降のシーダ ラッパーは、さらに音楽性の幅を広げていきます。
『BREATHE』などの作品では、“実験とチャレンジに満ちたニューアルバム”と紹介されることも多く、サウンド面でもよりポップで開けた方向性が強まっていったと言われています。
一方で、リリックの芯にあるのは相変わらずシリアスなテーマです。
ストリートのリアルを描きながらも、「生きる」「呼吸する」「それでも夢を見たい」といったモチーフが増え、重さと希望のバランスが絶妙な作風になっている、という評価も見られます。
近年のインタビューでは、若手との共演も積極的に行いながら、自分のスタイルをアップデートし続けていると語られていて、“レジェンドだけど今も現役で実験している人”という立ち位置だと受け取るファンも多いようです。
シーダ ラッパーの音楽性をざっくりまとめると、
- 初期:英語多め・高速フロウ・ハードでダーク
- 「花と雨」:日本語リリック増加・メロウで感情的
- 以降:ポップさも取り入れながら、深いテーマを描く
という流れで変化してきた、と整理できそうですね。
引用元:引用元:https://pucho-henza.com/seeda-profile/
参照元:https://chillchair.tokyo/hanatoame-historical-masterpiece-3reasons
参照元:https://tower.jp/article/interview/2010/08/18/68770
♯シーダラッパー
♯SEEDA花と雨
♯ラップスタイルの変化
♯日本語ラップ名盤
♯バイリンガルMC
クルー・コラボ・ニートTokyo|シーダ ラッパーの“動き方”を整理

SCARSとストリート発クルーでの立ち位置
シーダ ラッパーを語るとき、まず外せないのがクルー「SCARS」です。
SCARSはA-THUG、SEEDA、BES、STICKY、bay4k、MANNYらが集まった大所帯クルーで、ドラッグや金、ハスリングといったストリートの光景を、そのまま切り取ったリリックが話題になったと言われています。
2006年のアルバム『THE ALBUM』は、日本語ラップの“ワルさ”の基準を更新した1枚と評価されていて、クルー全員のラップスキルと生々しい描写が、のちの世代にも強い影響を与えたとされています。
その中心メンバーの一人として名前が挙がるSEEDAは、「ソロでも尖っているけれど、クルーの中にいるとさらに危うさが際立つ存在」として受け止められている印象がありますね。
CONCRETE GREENと客演・コラボの広がり
クルー以外の“動き方”としては、DJ ISSOとのMIXシリーズ『CONCRETE GREEN』も欠かせません。
このシリーズは、ストリート発の人気MIXとして知られており、SEEDAとDJ ISSOが日本各地のラッパーや海外勢をまとめ上げる場になってきたと言われています。
VOL.10や13では、これからのシーンを担う若手ラッパーを多数フィーチャーし、「次世代へのバトンを繋ぐコンピ」のような役割を果たしていると紹介されています。
最近ではT-Pablow「CRESCENT MOON」など、若手〜中堅ラッパーの客演にも呼ばれることが増えていて、シーダ ラッパーが“先輩枠”として参加する構図も目立つようです。
ニートTokyoという“場”を作ったシーダ ラッパー
ここ数年のSEEDAを象徴するのが、YouTubeチャンネル「ニートtokyo」での活動です。
ニートTokyoは、2017年末にスタートしたヒップホップ系インタビュー番組で、ラッパーやダンサー、お笑い芸人などに、数分間の一問一答を投げかけるスタイルが特徴だと説明されています。
主宰メンバーの一人として名前が挙がるシーダ ラッパーは、「誌面ではできないインタビューをやりたい」という編集者の相談に対して、海外のYouTubeチャンネルをヒントに企画を提案したとインタビューで語っています。
結果として、シーンの裏話や価値観が毎晩ネットに流れ、知らなかったラッパーを知る入口にもなっているので、「ラッパーとして出るだけでなく“場所を作る側”に回ったSEEDA」という見方もできそうです。
クルー、MIXシリーズ、インタビュー番組。
これらをまとめて眺めると、シーダ ラッパーは「自分の作品を出す人」以上に、「人と人、シーンとシーンを繋ぐハブ」として動いてきたのかな、と感じられますね。
引用元:引用元:https://pucho-henza.com/seeda-profile/
引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/SEEDA
参照元:https://ja.wikipedia.org/wiki/SCARS_(グループ)
参照元:https://spaceshowerstore.com/detail.php?goods_id=315
参照元:https://www.gqjapan.jp/culture/article/20210104-neet-tokyo
#シーダラッパー
#SEEDAクルー
#SCARS
#CONCRETEGREEN
#ニートTokyo
最新のシーダ ラッパー像と“親子星”世代のレジェンドとしての現在地

「親子星」が描く“今のシーダ ラッパー”
シーダ ラッパーの最新作『親子星』は、2012年の『23edge』以来およそ13年ぶりとなる11枚目のアルバムだと言われています。
Tiji Jojo、LEX、IO、D.O、VERBAL、Jinmenusagiら世代も色も違うラッパーが集結し、プロデュースにはBACHLOGICやZOT on the WAVE、KMなど、現在の日本語ラップを語るうえで欠かせない顔ぶれが並んでいるのも大きな特徴です。
インタビューでは、タイトル「親子星」には“お金にしがみつかず、それぞれが自分の光り方を見つける”というテーマが込められていると語られていて、家族や世代をまたいだ視点が強く意識されていると言われています。
かつて『花と雨』で心の闇や葛藤を描いたラッパーが、40代になった今は、生活感や家族との距離感も含めた“等身大のままの希望”をラップしている、という受け止め方も多いようですね。
“空白”ではなく、つねに動き続けてきたレジェンド
アルバムが13年ぶりだからと言って、その期間が止まっていたわけではありません。
シーダ ラッパーはYouTubeチャンネル「ニートtokyo」を主宰し、若手からベテランまでさまざまなラッパーの素顔を引き出す場をつくってきたと紹介されています。
さらに、国内大型フェス『POP YOURS』『THE HOPE』への出演や、次世代ラッパー発掘オーディション『RAPSTAR』の最年長審査員としての参加など、“表に立つ側”としてもかなりアクティブです。こうした動き方から、「作品は少なくても、シーンのど真ん中にはずっと居続けていた」という評価もあるようです。
“親子星”世代のレジェンドとしての現在地
1980年生まれのシーダ ラッパーは、いまや“親になった世代”の代表でもあります。
『親子星』にはZ世代のラッパーも多数参加していて、「自分と同世代のリスナー」と「その子ども世代のラッパー/リスナー」をつなぐハブのような役割を果たしている、と語られることもあります。
かつて“問題児”として語られたSEEDAが、今は若手に場所を渡しながら、自分も最前線でマイクを握る。
その姿が、“親子で同じラッパーを聴ける時代”のレジェンド像として、多くのファンに刺さっていると言われています。『花と雨』世代のリスナーにとっては、「あの頃の自分」と「今の自分と家族」をつなぐ一本の線のように感じられるかもしれませんね。
引用元:https://pucho-henza.com/seeda-profile/
引用元:https://spincoaster.com/news/seeda-11th-album-oyakoboshi
引用元:https://fnmnl.tv/2025/06/12/164516
参照元:https://realsound.jp/2025/04/post-1998550.html
参照元:https://cyzo.jp/culture/post_383571/
#シーダラッパー
#親子星
#日本語ラップレジェンド
#ニートTokyo世代
#花と雨から現在地