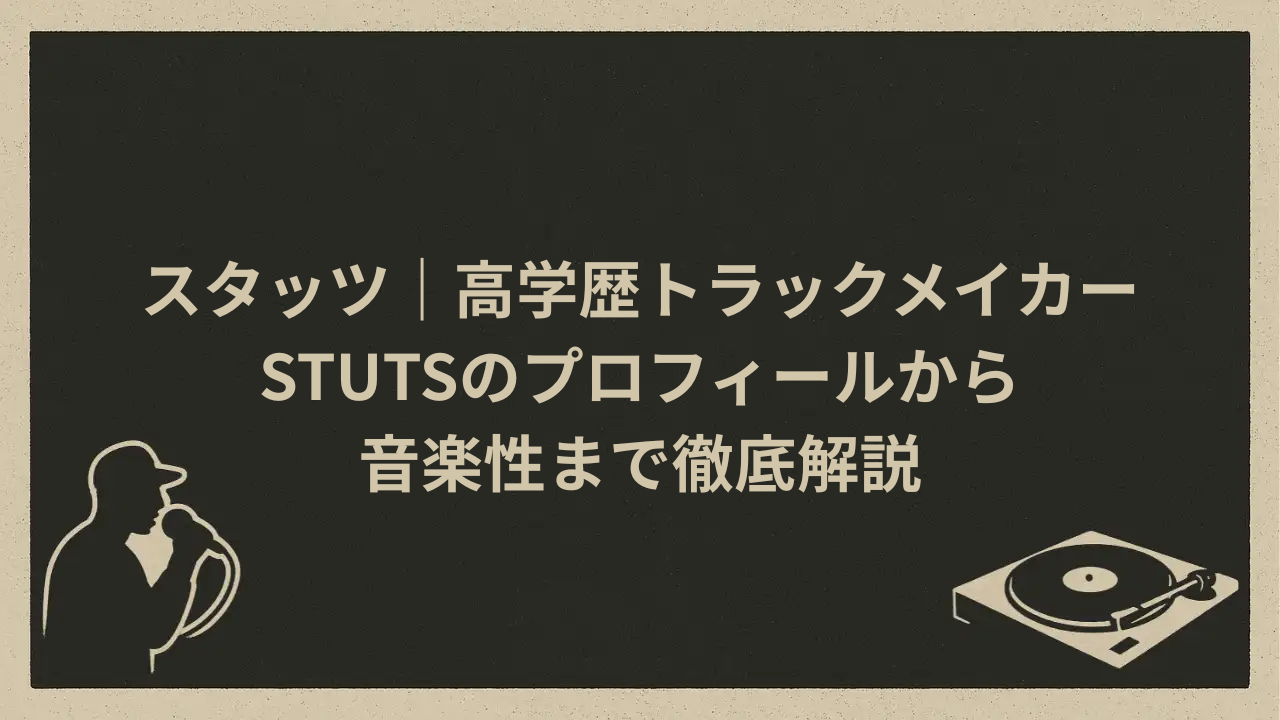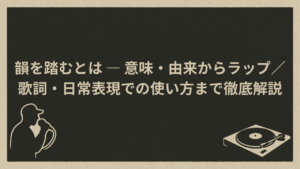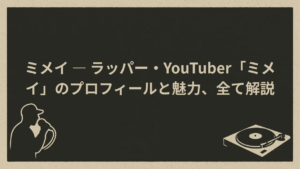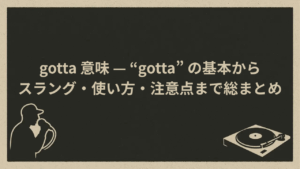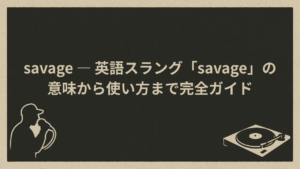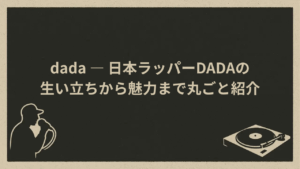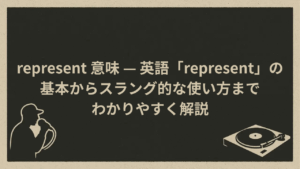H2:プロフィールと生い立ち
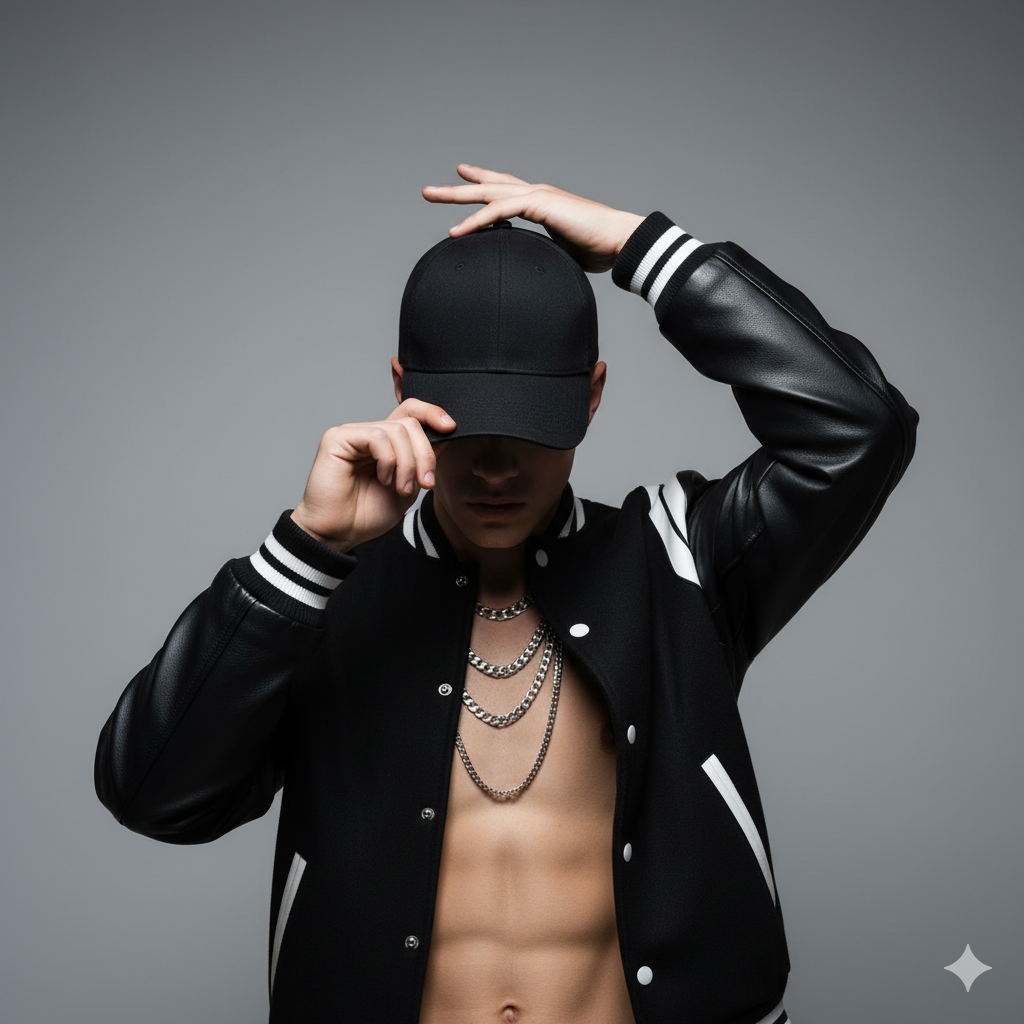
「スタッツという名前、音楽好きなら見聞きしたことありますよね。でも“スタッツ”って実は、ただのトラックメイカーじゃなくて、かなりユニークなバックグラウンドを持った人物なんです。今回はそのプロフィールと生い立ちを、会話風にサクッと整理してみましょう。」
H3:愛知県名古屋市出身/東大大学院卒という異色経歴
「ねえ、スタッツってどこ出身?」という疑問から始めると、彼は1989年6月23日生まれ、愛知県名古屋市出身と言われています。 参照元:『STUTSのプロフィール紹介|東大卒が目指す理想のラッパー像とは?』より。 pucho henza
その後、名門校「ラ・サール中学校・高等学校」を経て、なんと「東京大学農学部」に進学、さらに「東京大学大学院 情報学環・学際情報学府」の修士課程を修了したという“東大大学院卒”という異色の道を歩んだとも紹介されています。 参照元:『stuts 東大出身ビートメイカーSTUTSとは?』より。 HIP HOP BASE
「えっ、大学院まで?」と驚く声も聞こえてきそうですが、それよりも興味深いのが「幼少期から吃音症(きつおんしょう)を抱えていた」という点です。小学校4年生頃に自覚したとされ、その障壁を抱えながら音楽活動を本格化させていったと言われています。 参照元:『STUTSのプロフィール紹介|東大卒が目指す理想のラッパー像とは?』より。 pucho henza
中学・高校時代には、ラップやヒップホップに興味を持ち、サンプリング機器を購入するなど音の世界への没頭を始めたとも語られています。 参照元:Wikipedia『STUTS』より。 ウィキペディア
このように、スタッツの生い立ちは「学歴というスペック」+「音楽で表現したいという情熱」+「吃音というハンディキャップを抱えながら乗り越えようとしてきたストーリー」が三位一体になって伝わってくると言われています。
「なるほど、“ただ技がある人”じゃなくて、“背景がある人”なんだな」と思いながら聴くと、彼の作品やライブにも新たな見方が生まれるかもしれません。
「次回は、スタッツがどのようにして音楽シーンでキャリアを築いたのか、バトルではなくトラックメイカー/プロデューサーとしての道を一緒に見ていきましょう。」
#スタッツ #STUTS #東大大学院卒 #トラックメイカー #音楽プロフィール
H2:キャリアの歩み:トラックメイカーとしての台頭

「スタッツ(STUTS)ってラップを歌ってる人?それともビート作ってる人?」という声をよく耳にしますが、実は彼はトラックメイカー/プロデューサーとして頭角を現してきた人物と言われています。今回は、ラップ界の片隅からメジャーな音楽シーンへと進んだ彼のキャリアを、ゆるく掘ってみましょう。
H3:MPCでの路上パフォーマンスから全国的注目へ
「え、STUTSさんはどんな入り口から始まったの?」という疑問に対して、彼は高校時代に MPC を使ったストリートパフォーマンスに挑戦したことがターニングポイントだと語られています。参照元:GIRL HOUYHNHNM『WHO IS STUTS?』より。 girl.houyhnhnm.jp 当時、ニューヨーク・ハーレムで路上MPC演奏を行った動画が話題になり、国際的な反響も得たと言われています。
「路上で機材ひとつで勝負するって、すごい時代だなあ」と感じるかもしれませんが、この経験を通じて彼の名は徐々に広がりました。さらに2016年4月に1stアルバム『Pushin’』をリリースし、トラックメイカーとしての本格的な活動がスタートしました。参照元:HOUYHNHNM『A Composition Talk: STUTS & tofubeats』より。 ハイニム
このように、STUTSのキャリア初期は「ストリート」→「インディーリリース」→「全国/メジャー展開」という流れをたどったと言って良いでしょう。
H3:音楽的幅の拡大とコラボレーションで飛躍
「じゃあ、その後どう成長したの?」というと、STUTSは単なるトラックメイカーに留まらず、楽器演奏やボーカル参加、さらには国内外アーティストとのコラボにも挑戦しています。参照元:TOKION『The Boundlessness of Contrast by STUTS』より。 TOKION – カッティングエッジなカルチャー&ファッション情報 例えば、2021年から「Presence」シリーズやタイ・バンコクのバンド YONLAPA との楽曲 “Two Kites” にも関わるなど、活動の幅が明らかに広がってきたとも言われています。参照元:TOKION『STUTS and YONLAPA’s Vocalist Noi Naa…』より。 TOKION – カッティングエッジなカルチャー&ファッション情報
また、彼自身が「境界を超えたい」「拡張したい」という意欲を語っており、ジャンルや媒体を横断する姿勢が一貫して見られます。そんな背景も、彼がトラックメイカーとして“台頭した”理由の一つだと捉えられています。
――というわけで、スタッツの「トラックメイカーとしての台頭」についてざっくり整理しました。次回は「音楽スタイル・プロダクションの特徴」についても一緒に掘っていきましょう。
#スタッツ #STUTS #トラックメイカー #音楽キャリア #日本のヒップホップ
H2:音楽スタイル・プロダクションの特徴

「スタッツ(STUTS)って、ただ“かっこいいビートを作る人”ってイメージ、ありますよね。だけどその裏には、かなり緻密で多層的な音楽作りのプロセスがあると言われています。今回は彼の音楽スタイルとプロダクションの特徴を、会話形式で掘ってみましょう。」
H3:ジャズ/ヒップホップ横断のサウンドとMPC愛
A:「最近STUTSさんの曲聴いたんだけど、なんか“ジャズぽい”雰囲気もあるよね?」
B:「そうなんだよ。実はSTUTSさん、ジャズやソウル、ヒップホップを横断するトラックメイカーとして評価されていて、“MPC drum machineを使ってずっと作ってる”ってインタビューで語ってるの。参照元:TOKION『The Boundlessness of Contrast by STUTS』より。」 TOKION – カッティングエッジなカルチャー&ファッション情報
彼自身も「音は色や情景かもしれない」という感覚で制作していて、音とイメージをリンクさせながらトラックを構築してきたと言われています。参照元:同上。
つまり、スタッツのサウンド特徴には「ヒップホップのループ構造」+「ジャズ的コード進行/生演奏の要素」+「MPC/機材へのこだわり」が混ざっているわけです。
H3:生演奏・バンド編成を取り入れた最新プロダクション
A:「じゃあ、最近の作品と昔の作品で何が変わったの?」
B:「最新アルバム『Orbit』(2022)では、生楽器セッションやバンド編成での録音がかなり増えてて、ループから飛び出す構成も多いって記事で指摘されてるの。参照元:CINRA『STUTSのビートの「らしさ」はどこに宿る?』より。」 CINRA
この作品では、例えば即興的なスタジオ・セッションを録音して編集し、そこにキーボードやベースを後から加えるという手法が使われたとされています。生トラックの “息づかい” を取り込むことで、機械的なビート以上の“温度”が出ているとも言われてます。
また、バンドセットのライブも彼の音楽の特徴として挙げられており、「MPCプレイヤーがそのままフロントマンになる」というスタイル自体が珍しいと評価されているようです。参照元:FNMNL「インタビュー STUTS|Keep the Groove Going」より。 FNMNL (フェノメナル)
このように、彼のプロダクションには「ヒップホップ原点」+「演奏者視点」+「技術的こだわり」の3つが共存しており、それが“STUTSらしさ”と感じられる音になると言われています。
――というわけで、スタッツの音楽スタイル・プロダクションの特徴をざっと整理しました。次回は「代表曲・最新リリース・コラボレーション」についても一緒に見ていけたらと思います。
#スタッツ #STUTS #トラックメイカー #音楽プロダクション #ヒップホップーション
H2:代表曲・最新リリース・コラボレーション

「スタッツ(STUTS)ってどんな曲を出してるの?」という疑問を、会話形式で深掘りしてみましょう。彼の代表曲から最新作、さらには注目のコラボまで――音楽ファンなら押さえておきたいポイントを整理します。
H3:代表曲と知名度の高まり
「まず、どの曲が“代表曲”なの?」と気になるあなたに。STUTSの楽曲ランキングによると、「99 Steps (feat. Kohjiya / Hana Hope)」や「夜を使いはたして feat. PUNPEE」が上位に挙がっています。 JOYSOUND.com+1
例えば「夜を使いはたして」は、ノスタルジックな夜の情景をビートと歌詞で描いた一曲として“名曲の呼び声”を得ていると言われています。 girl.houyhnhnm.jp
このように、STUTSの代表曲には「クラブでも朝までリピートされる」「夜/明け方の空気を音で切り取る」ような特徴があり、リスナーの記憶に刻まれる作品になっています。
H3:最新リリース&注目コラボレーション
「じゃあ最新作は何?コラボもある?」という声にお応えすると、STUTSは2025年7月に EP『STUTS on the WAVE』をリリースしており、収録曲「Perfect Blue (feat. Tiji Jojo, Daichi Yamamoto, RYO‑Z)」など話題になっています。 STUTS – STUTS beats.
さらに、2024年には「Celebrate (with Jordan Rakei)」「いい湯だな (with 大貫妙子 & 江﨑文武)」など、多ジャンル・多国籍アーティストとのコラボによって活動範囲を拡張してきたとも紹介されています。 Billboard JAPAN+1
これらのコラボは、STUTSが“トラックメイカーとして国内ヒップホップだけに留まらず、グローバル・ジャンルを横断するクリエイターとして成長している”という印象を与えていると言われています。
――というわけで、STUTSの代表曲から最新リリース・コラボレーションまでざっとまとめました。次回は「初心者向け聴きどころガイド&これからの展望」について一緒に見ていきましょう。
#スタッツ #STUTS #代表曲 #コラボレーション #最新リリース
H2:これからの展望とファン必見の楽しみ方

「スタッツ(STUTS)ってこれからどこまで行くの?」というのが気になってるあなたへ、今後の展望とファンならではの楽しみ方を、雑談っぽく紐解いていきます。
「新作あるの?ライブどう楽しめばいいの?」といった疑問に寄り添って書いてみますね。
H3:今後の展望—ライブ規模の拡大&ジャンル越境
「まず、今後の展開ってどうなってるのかな?」と聞くと、STUTS自身がインタビューで「ライブ規模をもっと大きくしたい」「表現の幅をさらに広げたい」と語っていると言われています。参照元:『STUTS | Keep the Groove Going』より。 ([turn0search1]turn0search1)
たとえば、すでに武道館単独公演を経験しており、今後はアリーナ規模の公演も検討中という情報があります。参照元:同上。
また、音楽的にはヒップホップを軸にしつつも、ジャズ、ソウル、バンド編成などジャンルを越える動きが強まってきていて、「トラック提供だけじゃなくて、自分名義として“世界に届ける音”を作りたい」そんな意欲を持っているとも言われています。参照元:『WHO IS STUTS?』より。 ([turn0search0]turn0search0
つまり、ファンとしては「次のライブ・次の音源・次のコラボ」が“規模も内容も変わる”可能性があるという期待を持っておくと、より先取り感が出せそうです。
H3:ファンが楽しむためのポイント—ライブ・音源利用・参加型体験
続いて、ファン目線で「楽しみ方」のヒントをお届けします。まずはライブ。バンド編成やMPCプレイだけではなく、映像演出・観客との一体感・ゲスト出演者などが今後のステージで重要になってくると言われています。参照元:『STUTSインタビュー バンドとしての成熟を深め』より。 ([turn0search7]turn0search7
次に音源の利用。STUTS作品は「夜」や「朝」「移動」「都市生活」といったテーマ性が強くて、例えば「夜のドライブ」「作業BGM」「リラックスの時間」に使いやすい曲が多いと言われています。ライブ前や休日の“先取り感”演出にも使えそうです。
そして参加型体験。SNSでのハッシュタグ投稿やライブ会場でのコール&レスポンス、さらにはグッズや限定リリース(例えばアナログ盤など)をチェックしておくと、「ファンの仲間感」が高まるとも言われています。参照元:『WHO IS STUTS?』より。 ([turn0search0]turn0search0
このように、「これからの展望」と「楽しみ方」をリンクさせておくと、STUTSの音楽をただ聴くだけでなく“体験する”形に変えられると思います。
――というわけで、スタッツの“未来”と“ファンとしての楽しみ方”を整理しました。次回は、「代表曲・最新リリース・コラボレーション」を深掘りしたいですね。
#スタッツ #STUTS #今後の展望 #ライブ体験 #音楽ファン