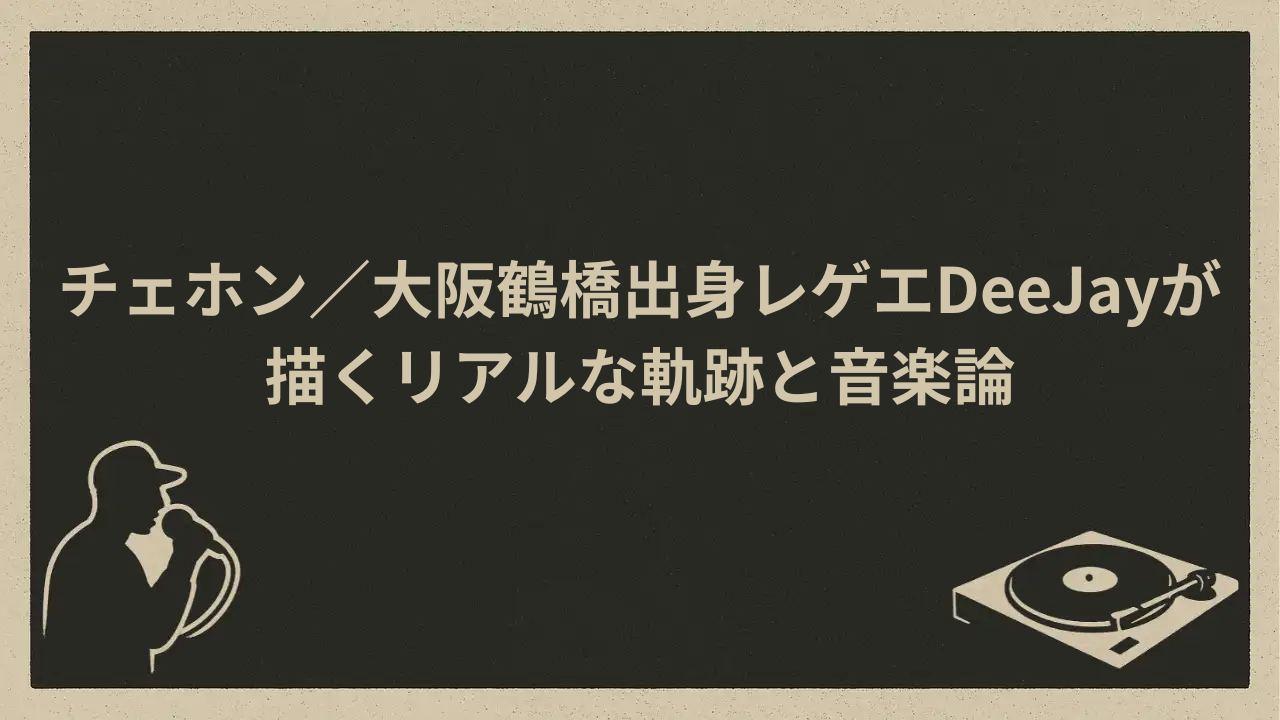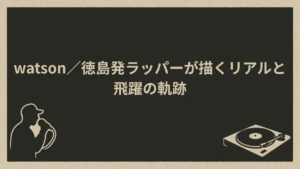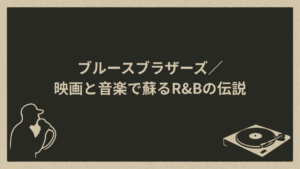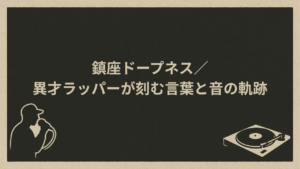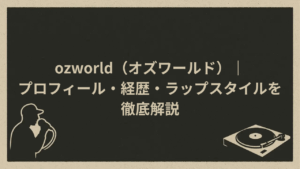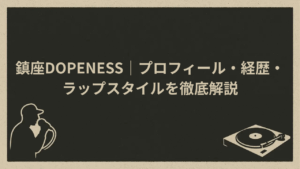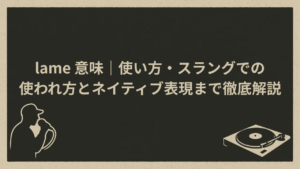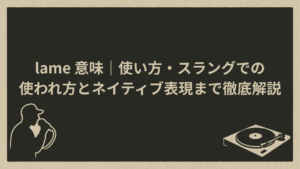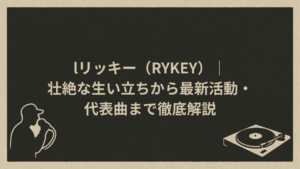チェホンとは?出身・ルーツ・音楽のきっかけ
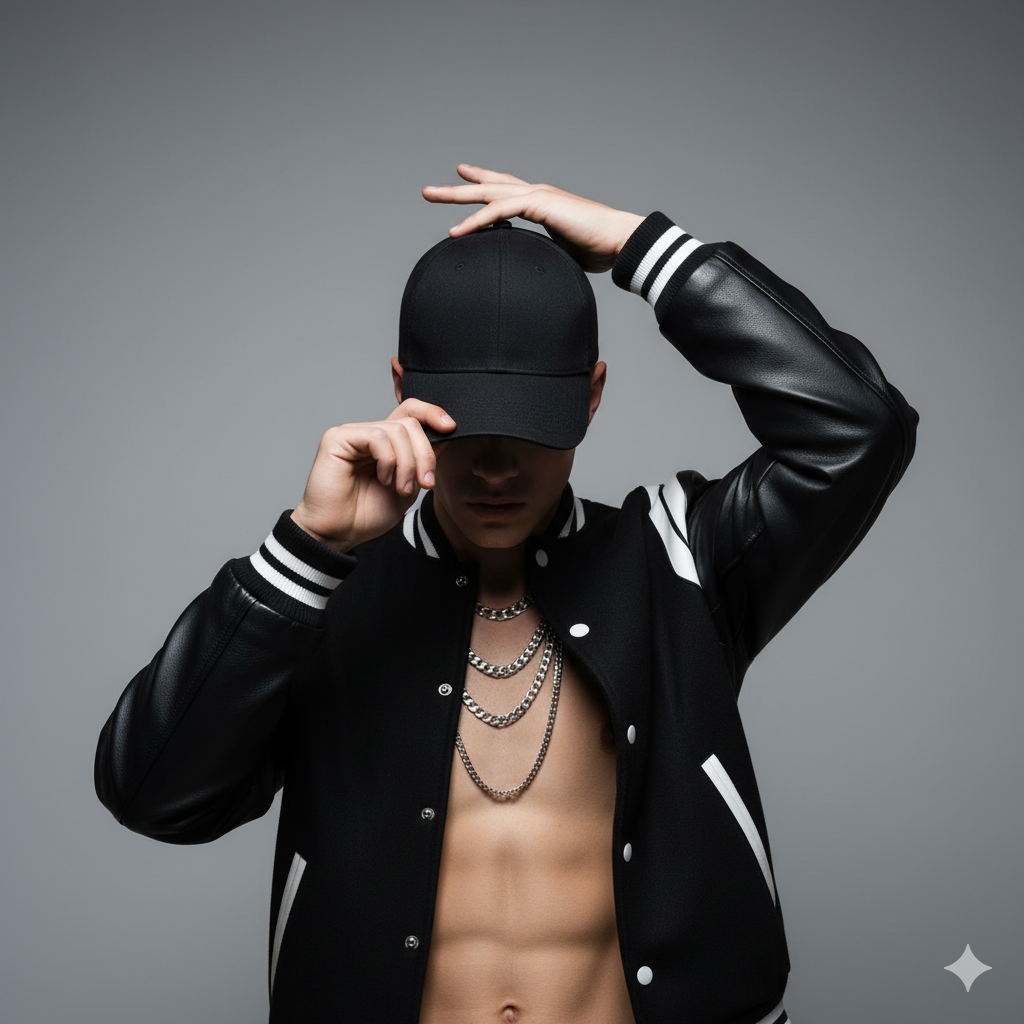
大阪・生野区鶴橋で育った“リアル”な原点
レゲエDeeJayとして日本の音楽シーンで強い個性を放ち続けるチェホン。彼のルーツは、大阪市生野区鶴橋という多文化が交差するエリアにあると言われています。コリアンタウンとしても知られるこの街で、在日韓国人三世として生まれ育ったチェホンは、日常的に日本語と韓国語が飛び交う環境に身を置いていたそうです。
「言葉」と「リズム」が交錯するこの地で育った経験が、彼の独特なリリックセンスやフロウに影響を与えたとする声もあります。幼少期から人前で話すことが苦手だった反面、言葉に対するこだわりは人一倍強かったとも語られています【引用元:https://pucho-henza.com/chehon-profile/】。
レゲエとの出会いは偶然から始まった
10代の頃、友人に誘われて訪れたクラブイベントで出会ったのがレゲエの音だったそうです。ヒップホップとは異なるリズム感、そしてパトワ(ジャマイカ英語)を用いたDeeJayスタイルに衝撃を受け、「これ、自分もやってみたい」と感じたのが最初のきっかけだったと語られています。
当時はまだラップとレゲエの境界がはっきりしていた時代。そんな中で、チェホンは「自分の声をそのまま武器にできる」というレゲエの魅力に引き込まれ、自宅で歌詞を書き、地元のクラブで少しずつマイクを握るようになっていったようです。
言葉とアイデンティティを武器にした表現者へ
彼の音楽には常に“リアル”があるとよく言われます。それは、自分の出自や地域性を飾らずに出す姿勢から来ているのかもしれません。
例えば、初期の楽曲では大阪弁をあえてそのまま使い、イントネーションすらもスタイルとして成立させていることが多く見られます。
また、チェホンのバックグラウンドには、学校での違和感や社会からの視線といった「マイノリティとしての葛藤」が根底にあり、それらを歌に昇華することで共感を呼んでいると言われています。
#チェホンとは誰か
#鶴橋出身のDeeJay
#在日ルーツとアイデンティティ
#レゲエとの出会い
#言葉で戦う表現者
キャリア初期〜メジャーデビューまでの歩み

地元クラブから始まった“マイク人生”
チェホンが音楽活動を始めたのは2002年頃、大阪・鶴橋を拠点とするクラブカルチャーの中でした。周囲にラッパーやDeeJayが多かった影響もあり、マイクを握るのはごく自然な流れだったとされています。当時は録音環境も十分ではなく、カセットやMDに自作の音源を録音し、仲間内で回していたという話もあるようです。
この時期からすでに「韻のキレ」と「ストリート感」を強く意識したスタイルを確立していたと言われており、ローカルのイベントではすぐに注目を集める存在になっていきました【引用元:https://pucho-henza.com/chehon-profile/】。
レゲエ界隈で名を広げた自主制作時代
2000年代前半は、日本におけるレゲエカルチャーの熱量が高まっていた時期でもあり、チェホンはその波に自然と乗る形で全国の現場へと活動の幅を広げていきました。自主制作でリリースされた音源や、他アーティストとのスプリット音源を通じて、「若手ながら存在感がすごい」と噂されていたようです。
この時期の代表的な活動には、大阪を拠点とするレゲエサウンドクルーとの共演や、サウンドクラッシュイベントでのDeeJay参加などが挙げられます。地道ながら確実に「現場叩き上げ」の経験を積み重ねていった過程は、現在のライブパフォーマンスにも活きていると言われています。
初の音源リリースと「みどり」で話題に
2006年、チェホンは自身の初のミニアルバム『みどり』をリリースします。タイトル曲「みどり」は、大麻や社会的価値観をテーマにしつつも、どこか柔らかく人懐っこいメロディラインと、日常の中にある“素の感情”を描いた歌詞が話題となりました。
「メッセージはあるけど、説教くさくない」――そんな絶妙なバランスが評価され、アンダーグラウンドだけでなく、ライトな音楽リスナーにも届いたと言われています。結果として、チェホンの存在はレゲエシーンを超えて広まり、2008年にはメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことになります【引用元:https://www.sonymusic.co.jp/artist/CHEHON/】。
#チェホンのキャリア初期
#みどりでブレイク
#大阪レゲエカルチャー
#DeeJayとしての地盤
#自主制作と現場叩き上げ
レゲエDeeJay/MCバトルで見せる多面性

リディムに乗せて放つ“チェホン節”の魅力
チェホンはレゲエDeeJayとしてのキャリアを通じて、圧倒的なリズム感とライブでの存在感を磨いてきました。ジャマイカ発祥の“DeeJayスタイル”を日本語で自然に乗りこなすそのスキルは、現場でも高く評価されてきたと言われています【引用元:https://pucho-henza.com/chehon-profile/】。
レゲエ独自のビート「リディム」に合わせて、緩急のあるフロウを刻むチェホンのスタイルは、どこか“言葉を楽器のように使っている”ようにも感じられます。テーマは社会問題から日常の小ネタ、さらには自分のルーツに触れるものまで幅広く、その内容も「メッセージ性」と「親しみやすさ」がうまく共存していると語られています。
一方で、過激な内容や社会的な問題を扱う際も説教くさくならず、言葉遊びとユーモアを交えて聴きやすく仕上げている点が、彼のDeeJayとしての腕前を示しているとも考えられています。
ラップバトルで発揮される“攻め”のスタンス
レゲエだけでなく、チェホンはラッパーとしても頭角を現しています。特に注目されたのが、MCバトルへの参戦。バトルといえば即興での言葉の応酬が醍醐味ですが、チェホンはその場の空気をつかみ、巧みに相手をかわす“柔の構え”と、一撃で観客を沸かせる“鋭さ”の両方を兼ね備えていると評されることがあるようです。
ラップバトルの文化はレゲエの「サウンドクラッシュ」にも通じる部分があり、チェホンにとっては“異分野”というより“もう一つの戦場”だったのかもしれません。実際、彼のバトルスタイルにはレゲエDeeJayで培った間(ま)や声の強弱が活かされており、ジャンルを超えてファンを増やしているとも言われています【引用元:https://www.youtube.com/watch?v=z2-l06Zy1ko】。
自由にジャンルをまたぐ“横断型アーティスト”として
チェホンは、レゲエとラップ、双方を武器にしながら活動の幅を広げてきました。どちらか一方に軸足を置くというより、その時の現場・空気・メッセージに応じてスタイルを使い分けている印象があります。
その自由さは、チェホンというアーティストの信条を表しているのかもしれません。“レゲエの人”“ラッパー”という枠に収まらないからこそ、彼の表現は常に新鮮で、多くの人に届きやすいとも考えられています。
#チェホンの多面性
#レゲエDeeJayの魅力
#ラップバトルでの存在感
#ジャンル横断の表現力
#言葉とリディムの融合
音楽性・影響力・代表曲の魅力

“ジャマイカ仕込み”の本格レゲエスタイル
チェホンの音楽性を語る上で欠かせないのが、2005年に渡ったジャマイカでの“修行”経験です。現地で生活しながらDeeJayスタイルを学び、本場の空気とリズムを自分の中に取り込んでいったことで、彼の音楽はより“リアル”なものへと深化していったと言われています【引用元:https://pucho-henza.com/chehon-profile/】。
日本語でレゲエをやる――それ自体が難易度の高い挑戦にも関わらず、チェホンはリディムのグルーヴを崩さず、言葉を自然に乗せる技術を体得。結果として、彼の楽曲には“日本人離れした”という形容がつくこともあるようです。ただ、本人は「レゲエに日本語をのせるのは当然」と語っていたともされており、その自然体の姿勢が逆に評価されているようです。
リスナーの心を打つ“言葉の選び方”
チェホンのリリックは、攻撃的なものだけではなく、どこか優しくて、時に切ない。「韻を踏む」ことよりも「伝わる」ことに重きを置いているように感じる――そんな意見が多く聞かれます。
たとえば代表曲「みどり」では、賛否のあるテーマを扱いながらも、押し付けではない語り口で、聴く人に“考えさせる余白”を残しています。一方、「韻波句徒」ではテクニカルなラップとメッセージ性が融合し、レゲエとヒップホップの垣根を超える試みとして注目を集めました。
彼の曲を聴くと、ラフな言い回しの中にも“詩人”的なセンスが光っていると感じる瞬間があります。それは、言葉と向き合い続けてきた彼ならではの視点かもしれません。
若手アーティストへの影響力とシーンへの貢献
チェホンは単に“カリスマ的な存在”であるだけでなく、後進のアーティストに対しても強い影響を与えてきた人物だと考えられています。
彼のように、自らのルーツや個性を堂々と表現するスタイルは、マイノリティ出身や地方アーティストにとって“突破口”となった可能性もあると指摘されています。
また、ライブでは若手と共演する機会も多く、現場を盛り上げながら“シーン全体の底上げ”にも貢献していると見る声もあるようです。
#チェホンの音楽性
#ジャマイカ修行経験
#代表曲みどりと韻波句徒
#日本語レゲエの可能性
#後進への影響と貢献
今後の展望とファンが注目すべきポイント

ジャンルを超える自由な動きに期待
チェホンのこれからを語る上で欠かせないのが、“ジャンルに縛られない姿勢”です。
もともとレゲエDeeJayとしての活動が中心でしたが、ここ数年ではラップやR&B、さらにはソウル寄りのアプローチも取り入れ始めていると言われています。特にYouTubeやライブ配信を通じて披露される楽曲には、ジャンルの境界を感じさせない自由さがあり、「あえて型にはまらないことを選んでいるのでは」と見る声もあるようです【引用元:https://pucho-henza.com/chehon-profile/】。
それは音楽性だけでなく、コラボレーションの幅広さにも表れており、若手アーティストやジャンル外のミュージシャンとの共演も今後増えていくのではないかと予測されています。
“現場感”を大切にするライブ活動の進化
ライブに足を運んだことのある人なら分かると思いますが、チェホンのライブは“音源以上に熱量がある”と感じさせてくれるもの。
最近では、地方イベントやインディペンデントなライブにも積極的に出演しており、SNSを通じて「今、ここでしか味わえない空気感」を発信しています。
このような“現場主義”のスタンスは、ファンとの距離を縮めると同時に、新たなリスナー層にも響いているようです。今後も大箱だけでなく、小規模なスペースでのライブやトークイベントなど、“人と空間”を大切にする活動が続いていく可能性があると考えられています。
SNSや音源配信での“日常発信”にも注目
チェホンは、InstagramやYouTubeでの発信もアクティブです。ステージでの姿とは違う、日常の何気ない投稿やリリックの断片などが、不思議と心に残る…そんな魅力があります。
特にYouTubeでは、即興フリースタイルや未発表音源の断片を公開することもあり、「これが正規リリースされるのか?」と話題になることもしばしば。
音楽と日常を自然に結びつけて発信していくスタイルは、今後さらに広がっていくのではないかと期待されています。
#チェホンの今後
#ジャンルを超える音楽性
#現場主義のライブスタイル
#SNSでの発信力
#若手アーティストとの共演に注目