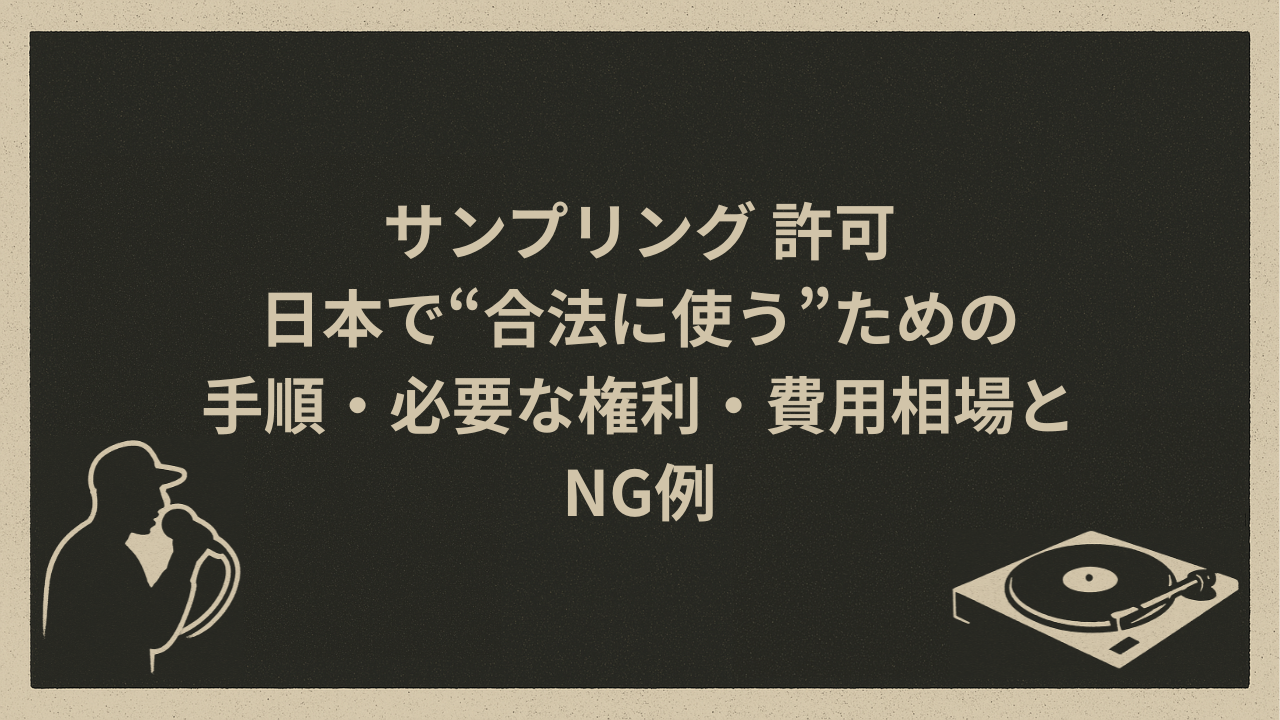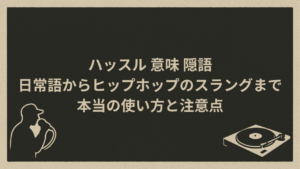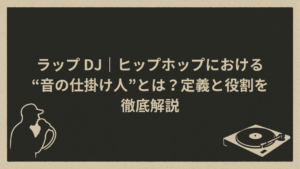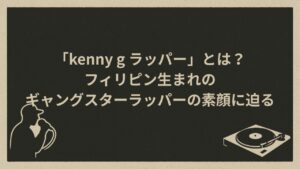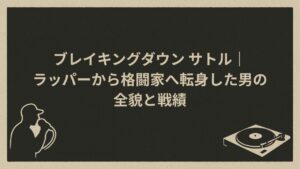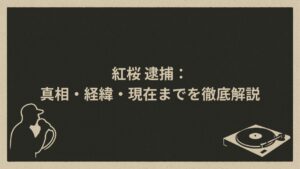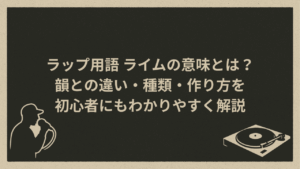サンプリングで「許可」が要る理由と、対象となる権利の全体像

権利の“二層構造”をサクッと整理
サンプリングで押さえたいのは、録音物に関わる「原盤(=著作隣接権)」と、作詞・作曲に関わる「楽曲(=著作権)」という二系統が並走している点です。実務では、原盤側はレコード会社や製作者の許可、楽曲側は著作者・出版社(管理団体経由のことも)の許可が別々に必要になると言われています。どちらか一方だけでは足りず、利用条件(用途・媒体・期間・地域など)も個別にすり合わせるのが基本だと説明されています。BIG UP!+1
日本に“包括的フェアユース”はない——「数秒ならOK」は誤解
「短ければセーフ」という都市伝説が広がりがちですが、日本法には米国のような包括的フェアユース規定がなく、長さや加工度合いだけで自動的に許されるわけではない、と解説されています。結局は権利と利用実態の整合が求められる、という理解が安全だと言われています。ウィキペディア
「雰囲気が似ている」ケースはどこを見る?
原盤をそのまま取り込むのではなく、“生演奏で似せた”などのケースは、通常は原盤侵害ではなく、メロディ等の楽曲著作権の問題として判断されやすい、と解説されています。つまり「音源をコピーしたのか」「楽曲要素が実質的に同一・類似なのか」で論点が分かれる、という視点を持つと迷いにくいです。実務では「似ているライン」を巡って争いも起きやすいので、参照事例や専門家の解説を当たりに行くのが無難だと言われています。KAI-YOU Premium
(※画像を引用する場合は「参照元:URL」、文章を引用する場合は「引用元:URL」を明記してください)
#サンプリング許可
#原盤権と著作権
#フェアユースは日本に無い
#数秒でも注意と言われています
#似ている問題と判断基準
許可の種類と窓口:誰に何を取る?(実務フロー)

楽曲側(作詞・作曲)—管理確認→出版社・著作者へ
まずはJASRACの作品データベース「J-WID」で管理状況と作品コードを確認します。複製や配信など自分の利用区分が管理対象かを見て、×(非管理)や出版社直轄の表示なら別窓口へ進む、という順番が基本だと言われています。www2.jasrac.or.jp+1
注意したいのは編曲(歌詞・メロ変更を伴う利用)。ここは管理団体の包括処理ではなく、著作者や音楽出版社に個別許諾を求めるのが原則と案内されています。つまり、J-WIDで出版社情報を拾い、出版社窓口に照会→条件提示→書面化、という流れを踏むと迷いません。JASRAC
原盤側(録音物)—レコード会社・実演家の許諾
録音そのものを使う場合は**原盤(著作隣接権)**の処理が別立てです。窓口の手がかりは日本レコード協会(RIAJ)の「音源利用許諾窓口一覧」。レーベルごとの連絡先がまとまっており、用途や範囲を添えて問い合わせる、という実務が推奨されています。場合によってはブライダル等の特定用途の手続きも案内が用意されています。日本レコード協会+1
NexToneを使うケース—PlayNで申請→許諾マーク
管理がNexToneの作品・利用形態なら、オンラインシステムPlayNから申請できます。利用者登録→区分選択→申請の順で進み、承認後に許諾番号と許諾マークが発行され、サービス画面の見える場所に掲示すると説明されています。目安として「申請日から第5営業日以内」に番号発行と記載があります(不備除く)。株式会社NexTone(ネクストーン)+1
海外曲・専属楽曲—“出版社先行”と専属解放の確認
外国作品では、JASRAC手続の前にサブパブリッシャーの同意を取得する運用が示されています。出版社の指定料率や最低使用料が適用される場合もあるため、J-WIDで出版社表示を確認し、該当する出版社へ可否と条件を照会する、という順が安全だと言われています。JASRACの案内ページでも、特定の出版社が並記される場合は並行して出版社連絡が必要/利用不可の注意が明記されています。JASRAC+1
(※画像引用は「参照元:URL」、文章引用は「引用元:URL」を明記)
#サンプリング許可
#JASRACとJ-WID
#原盤権の窓口RIAJ
#NexToneとPlayN
#海外作品は出版社先行
費用相場・審査の期間感・交渉ポイント

料金は“ケースごとに設計”——前払金+持分の発想
サンプリング許可の費用は、用途(商用/非商用)、秒数、露出規模、流通範囲で大きく変わると言われています。実務では、著作権側は前払金(最低保証)+パブリッシングの持分で提示されることがあり、原盤側はマスター使用料を個別に交渉する流れが一般的だと解説されています。特にヒット曲や広告用途では、短尺でも条件が上がりやすい、と紹介されています。LANDR Blog+1
審査〜許諾番号までの流れと“請求サイクル”
管理がNexToneの場合、利用者登録→PlayNで申請→承認後に許諾マーク/許諾番号が発行され、サービス画面の見える場所に表示するよう案内されています。許諾後は利用実績を報告し、NexToneの請求スケジュールに沿って請求書が発行される——というのが基本線です。ガイドには、配信期間に応じて「請求書発行→支払期限」の目安が示されており、繰り越しや期限延期は原則行わない旨も記載されています。株式会社NexTone(ネクストーン)+2株式会社NexTone(ネクストーン)+2
用途別の“目安表”を見て初期見積りを固める
ブライダル(結婚式・披露宴)や映像同梱メディアなど、用途別の手続きページや**使用料早見表(PDF)**が公開されており、表示方法(許諾マークの掲示箇所)や請求のタイムテーブル、見積りの考え方を事前確認できます。ブライダル向けページでは、申請→確認完了後に許諾マーク・番号・許諾書が発行され、支払い期日の一覧(例:3月末申請→5月末請求書→6月末支払い など)が明示されています。株式会社NexTone(ネクストーン)+1
交渉のコツ——“使い方の具体化”で条件を下げる余地
どこで何秒使うのか、加工の程度、地理・期間・媒体、想定再生回数といった利用条件の具体化は、見積りの根拠になりやすいと言われています。代替案(短尺化、別テイク、クリアランス済み音源の活用)も併記すると、交渉がスムーズになりやすい——こうした段取りが実務では推奨されています。LANDR Blog
(※画像を引用する場合は「参照元:URL」、文章を引用する場合は「引用元:URL」を明記してください)
#サンプリング許可
#費用相場は個別交渉
#NexToneとPlayN
#許諾番号と請求サイクル
#用途別早見表で事前設計
ありがちなNGとグレー:やってはいけないケース集

「商用じゃない・無料公開・プロモ用」でも要クリアランス
「収益化してないから大丈夫」「宣伝用に少しだけ」——この発想は危ういと言われています。使用の有無は権利処理の要否と直結し、長さや加工の程度が免責になるわけではありません。実務解説でも、原盤(録音物)と楽曲(出版/著作)をそれぞれ処理しないと拒否や法的リスクに発展しかねない、という整理が繰り返し示されています。特にヒットや広告接触が増えると条件が厳格になりやすい点も踏まえ、最初から許諾前提で設計するのが無難だと言われています。 LANDR Blog
「数秒・数小節ならOK」は都市伝説
日本では包括的フェアユース規定がなく、“何秒までOK”という明確免責ルールは存在しないと整理されています。取扱いはケースバイケースで、短尺の切り出しやワンショットでも問題化し得る——この点は近年の法務・実務解説や事例紹介でも度々言及されています。判断を誤ると、公開後に差し止め・収益分配の再交渉を迫られるおそれがあるため、リリース前の照会・書面化が推奨されています。 KAI-YOU Premium+1
管理団体は「編曲許諾」を代行しない
歌詞変更・メロディ改変・替え歌などの編曲に関する許諾はJASRACの包括対象外と案内されています。J-WIDで作品の管理状況を確認したうえで、音楽出版社や著作者へ個別照会→条件合意→書面化という手順を外すと、申請が差し戻しになることがあると言われています。窓口や「×(非管理)」表示の読み方もJASRAC公式で明示されているため、事前にチェックしておくと迷いにくいです。 JASRAC+2JASRAC+2
Type Beat/フリー音源の“規約未読”は地雷
Type Beatやフリー配布のビートでも、商用不可・要クレジット・再配布禁止など細かな条件が規約に定められているケースが多いと指摘されています。元ネタに著作物が含まれていたり、サンプルパックの規約を越えた再利用をすると、あとから配信停止・収益没収・申立てに繋がるおそれがあります。配信代行やプラットフォームごとの細則も確認し、「購入=無条件に自由」ではない前提で進めるのが安全だと言われています。 BIG UP!+2BIG UP!+2
(※画像を引用する場合は「参照元:URL」、文章を引用する場合は「引用元:URL」を明記してください)
#サンプリング許可
#数秒神話はNG
#編曲は出版社へ要照会
#TypeBeat規約要確認
#公開前に書面化が安心
今日から使えるチェックリスト&テンプレ(連絡文例つき)

まずは実務チェックリスト
1)J-WIDで管理確認:作品コード・出版社の表示を取得(「各種連絡先」から出版社や海外窓口も辿れます)。J-WID
2)編曲等の可否を出版社/著作者へ照会(歌詞・メロ改変は団体包括の外側と言われています)。ヤマハミュージック
3)原盤権者へ利用可否照会:レーベルの連絡先はRIAJの「音源利用許諾窓口一覧」から。日本レコード協会
4)条件の整理:範囲/媒体/期間/地域/収益形態を明文化。
5)表示事項:許諾マーク・許諾番号の掲示位置を確認。株式会社NexTone(ネクストーン)
6)書面化と保管:承認メールや許諾書、番号の控えを残しておくと安心と言われています。note(ノート)
連絡テンプレ(貼り付けて使える要旨)
件名:サンプリング利用可否のご相談(作品名:___)
いつもお世話になっております。__(氏名/団体名)と申します。
作品「___」の以下箇所を、__(曲名/映像名)でサンプリング利用したく、可否と条件をご教示ください。
・使用箇所と長さ:冒頭フレーズ 0:12–0:18(約6秒)
・加工内容:ピッチ−2、タイムストレッチ+5%、ループ化
・媒体/地域/期間:音楽配信(Spotify/Apple)、全世界、1年間
・収益形態:配信収益分配(広告・サブスク)
・公開予定日:2025/12/01(目安)
・想定リーチ:初月1万再生程度
・クレジット案:“Contains a sample of ‘___’ (P) 20XX Label / (C) 20XX Publisher”
必要であれば追加資料を提出します。ご検討のほどよろしくお願いいたします。
※NexTone管理の場合は、PlayNで申請→承認→許諾マーク/番号の表示→実績報告→請求・支払の順で進むと説明されています。株式会社NexTone(ネクストーン)+1
代替案:クリアランス済みカタログを使う
「時間がない/交渉が難航しそう」という時は、Tracklibのような“あらかじめ権利処理設計がある音源”を検討する手もあります。掲載曲は申請〜審査〜許可の流れが整備され、個人でも手続きしやすいと紹介されています。block.fm
#サンプリング許可
#JWID検索
#原盤窓口RIAJ
#NexTone許諾マーク
#Tracklib活用