生い立ちとKOHHとしてのキャリアの始まり

音楽シーンで 千葉雄喜 という名を耳にしたとき、「KOHHとしての姿しか知らない」と感じる人も少なくないはずです。そこで今回は、そのルーツを少し掘り下げ、彼の原点を覗いてみましょう。
東京都北区王子出身、KOHH名義での2008年からの活動開始、プロデューサーとの出会いからミックステープリリースへ
千葉雄喜は1990年4月22日、東京都北区王子で生まれたと言われています(引用元:日本語Wikipedia)(ウィキペディア)。混沌とした家庭環境の中で育ち、幼少期を通じて抱いた“自分の声を響かせたい”という思いが、音楽への道を自然と開いていったようです(複数ソースよりまとめ)。
本格的に音楽制作を始めたのは 18歳ごろのこと。ここでプロデューサーの「318(高橋良)」と出会い、レーベル「GUNSMITH PRODUCTION」下で活動をスタートさせたのは大きなターニングポイントだったと言われています(BELONG Media)。
2012年11月には、衝撃の音源『YELLOW T△PE』を自主制作のミックステープとして発表しました(「処女作」としてのミックステープ、とも紹介されています)(iFLYER)。このリリースが徐々に話題を呼び、日本語ラップの新しい感覚を提示するきっかけになったとされています。
その後2013年には『YELLOW TAPE 2』をリリース。この頃、「KOHH」という名前が徐々に音楽シーンに浸透し始めた、という流れも読み取れます。
このように、KOHHとしてのキャリアは、北区王子というローカルな出自を持つ青年が、自主制作から始まり、プロデューサーとの出会いを経て急速に注目を集める稀有な成長ストーリーとして語られているようです。その根底には、家族や自分自身との対峙、そして「自分の声を届けたい」という強い衝動があったと言われています。
#千葉雄喜
#KOHH誕生
#生い立ち
#日本語ラップ
#ミックステープ時代
国内外への飛躍:作品とコラボの軌跡

KOHH(本名:千葉雄喜)のキャリアは、日本のヒップホップシーンを駆け上がるだけにとどまらず、国境を超えた広がりを見せていると言われています。ここでは、彼の代表作や国際的なコラボレーションを通じて、彼がどのようにその存在感を高めてきたのかを整理してみました。
VICE特集、アルバム『MONOCHROME』『梔子』『DIRT』のリリース、Keith Ape「It G Ma」への客演、海外フェス出演などの要点
2014年、KOHHは日本のユース向けメディア VICE において、日本人HIP‑HOPアーティストとしては初めて特集されたとされています。これは、彼のシーン内外での注目度が高まった重要なきっかけの一つだったと言われています (ウィキペディア, LIVERARY)。
その後、2014年7月にはセカンド・アルバムとして 『MONOCHROME』 をリリース。iTunesのHIP‑HOP/ラップカテゴリで1位、総合チャートでは6位を記録するなど、異例のスターターを切ったと言われています (LIVERARY)。そして2015年1月1日にはファースト・アルバム 『梔子(くちなし)』 を発表。さらにiTunesで総合・HIP‑HOPチャートともに1位を獲得しました (ウィキペディア)。
同年、KOHHは韓国のアーティスト Keith Ape のヒット曲「It G Ma」に客演として参加。この楽曲のMVは公開から1ヶ月で再生数が100万回を超え、日本だけでなく海外でも話題になったと伝えられています (ウィキペディア)。このコラボによって、KOHHは国際的な舞台にその存在を印象づけることとなったようです。
さらに、2015年10月には3枚目のアルバム 『DIRT』 をリリース。10月末のリリース後、12月27日には「DIRT CONCERT & GALLERY」をLIQUIDROOMで開催し、チケットはわずか1分で完売したと言われています (ウィキペディア)。
KOHHの国内での評価は、ヒップホップの本質を突くリリックと、既存の枠を壊すアティチュードとともに高まっていったようです。さらに、「It G Ma」への参加や海外メディアの注目などを通じて、ボーダーレスにその影響力を広げ続けたと言われています。彼の活動は、まさに日本のラップを世界へとつなぐ先駆けともいえる存在と言えるでしょう。
#KOHH作品
#日本語ラップ進化
#ItGMa
#国際コラボ
#HIPHOP展開
KOHHからの引退宣言と『The Lost Tapes』への橋渡し

音楽活動を通じて多くの軌跡を残してきたKOHHこと千葉雄喜ですが、2020年以降、活動に大きな変化が見られた時期があります。ここでは、「いったん幕を閉じた形」とされる“引退”と、その後の活動再開へとつながる重要作品『The Lost Tapes』について整理してみます。
2020〜2021年の“Worst”アルバムと引退、2022年に『The Lost Tapes』リリースによる活動の一時整理
2020年4月、KOHHはアルバム 『Worst』 をリリースしました。タイトルからも伝わるように、これまでの自分を否定するような作品であり、「引退への序章では?」と噂されたこともあるそうです。実際、翌年には“KOHHとしての活動を終了する”というメッセージ性が強まった時期でもありました(音源リリース情報より) (TuneCore Japan)。
その静かな期間を経て、2022年9月25日に 『The Lost Tapes』 をリリース。これは公式アルバムとしては活動休止期を挟んでの復活作であり、未発表トラックや未整理の音源をまとめたコレクション的な位置づけで、多くのファンにとって「橋渡し的作品」だったと言われています (Apple Music – Web Player, TuneCore Japan)。
『Worst』が「終わり」をテーマにした閉塞感のある作品だとすれば、『The Lost Tapes』は一種の整理・総括のような意味合いを帯びているとも受け取れます。ファンコミュニティでも「見えなくなっていたKOHHの輪郭が、The Lost Tapesで再び輪郭を持ち始めた」という声があり、次なる展開への期待感が高まったのではないかと思われます。
KOHHが本名=千葉雄喜へと切り替えたのはこの時期ですが、その流れの中に、過去と未来をつなぐ意識的なリリースがあったことは確かです。こうして『The Lost Tapes』は、リスナーにとって「あぁ、また始まるんだな」という期待を自然と抱かせる作品となったようです。
#KOHH引退
#Worstアルバム
#TheLostTapes
#音楽の再構築
#千葉雄喜
千葉雄喜としての新たな出発とグローバル展開

KOHHというアーティスト名で知られた千葉雄喜さんが、“本名”名義で再び音楽活動を開始した2024年2月以降、彼のキャリアには新たな展開と国際的な注目が加速したと言われています。
2024年2月、本名での音楽活動再開「チーム友達」をリリース、さらにMegan Thee Stallionとの「Mamushi」コラボで米ビルボード初登場
2024年2月13日、KOHHとしての活動引退以来、初となる新作 「チーム友達」 を“千葉雄喜”名義で緊急リリース。音源とミュージックビデオは同日に公開され、SNSでバズるなど、一気に話題沸騰したとされています(引用元:The First Times)(THE FIRST TIMES)。記事によると、歌詞とMVのユーモア、リミックス展開などが複合的に広がりを見せ、ネット上で社会現象とも言える反響があったようです(THE FIRST TIMES, カルチャーメディアNiEW(ニュー))。
そして同年7月、アメリカのグラミー受賞ラッパー Megan Thee Stallionの楽曲「Mamushi」(アルバム『Megan』収録)に参加。TikTokでバイラル化し、米ビルボード Hot 100チャートで 45位 にランクイン。これは千葉雄喜にとって、アメリカのメインチャート初登場だったと言われています(note.com)。
このように「チーム友達」での復帰から、「Mamushi」での米チャート入り—この流れは、まさに 国内から世界へと活動を拡大するステップだったとする見方ができます。TikTokやSNSを介したグローバルな波及力とともに、本名での再出発がアーティストとしての新章にふさわしい幕開けになると語られています。
#千葉雄喜
#チーム友達
#Mamushi
#MeganTheeStallion
#国際進出
多面的な才能と現在の活動範囲

ラッパーとしての活動だけに留まらず、千葉雄喜(元KOHH)は今、文芸・ファッション・アート・店舗運営など多彩な領域に自らの表現を広げています。そのクリエイティブな幅広さは、“音楽だけじゃない人間像”を描く上で欠かせない要素だと言われています。
文芸誌連載、ファッション・アート領域での活動、店舗運営、多才ぶりとアーティストとしての広がり
まず注目したいのは、文芸誌『文學界』への連載開始です。2023年12月より、「千葉雄喜の雑談」というタイトルで連載がスタートし、“KOHHを引退して2年。今、千葉雄喜が考えていること、していること”をテーマに綴っていると紹介されています(引用元:CINRA/ナタリー)(CINRA)。これは、音楽以外の表現領域で自身の内面を丁寧に描こうとする意欲の表れとも受け取れます。
さらに、ファッション・アートの分野でも存在感を発揮しています。**セレクトショップ「Dogs(ドッグス)」**の運営に関わり、北区王子を拠点に店舗オープンやライブイベントの開催も行っていると報じられています(引用元:Hypebeast Japan)(Hypebeast)。加えて、PARCO渋谷内での「THOM BROWNE」ショップクルーズへの出演を通じて、服装やスタイリングを通した新たな表現も披露しています(引用元:PARCO特集)(渋谷PARCO-パルコ-)。
また、アートや創作活動にも積極的に取り組まれているようです。SKY‑HIとの対談では、「絵を描く」「本を読む」「服を作る」「動画や写真を撮る」と、様々なメディアでの自己表現を楽しんでいると語っており、それが作品の幅広さにつながっているとされます(引用元:SKY‑HI対談)(miyearnZZ Labo)。
これらの活動を通じて、千葉雄喜は単なるミュージシャンではなく、“文化クリエイター”としての存在性を深化させているように見えます。言葉を紡ぐ感性だけでなく、視覚や思想を含めた表現に領域を広げ、「音楽×読む・見る・着る・体験する」という複合的な場づくりを自らの手で進めている姿が印象的です。
こうした多面的な活動から見えてくるのは、千葉雄喜という人物が“限界を自ら設けず、自身の感覚に従って創作を続けるアーティスト”であるということです。音楽を通じて人々とつながり、文字や展示で心を揺さぶり、服や場を通じて世界と対話する——この自由な姿勢こそが、今の彼の魅力なのではないでしょうか。
#千葉雄喜
#文學界連載
#Dogsセレクトショップ
#THOMBROWNE表現
#多才なクリエイター
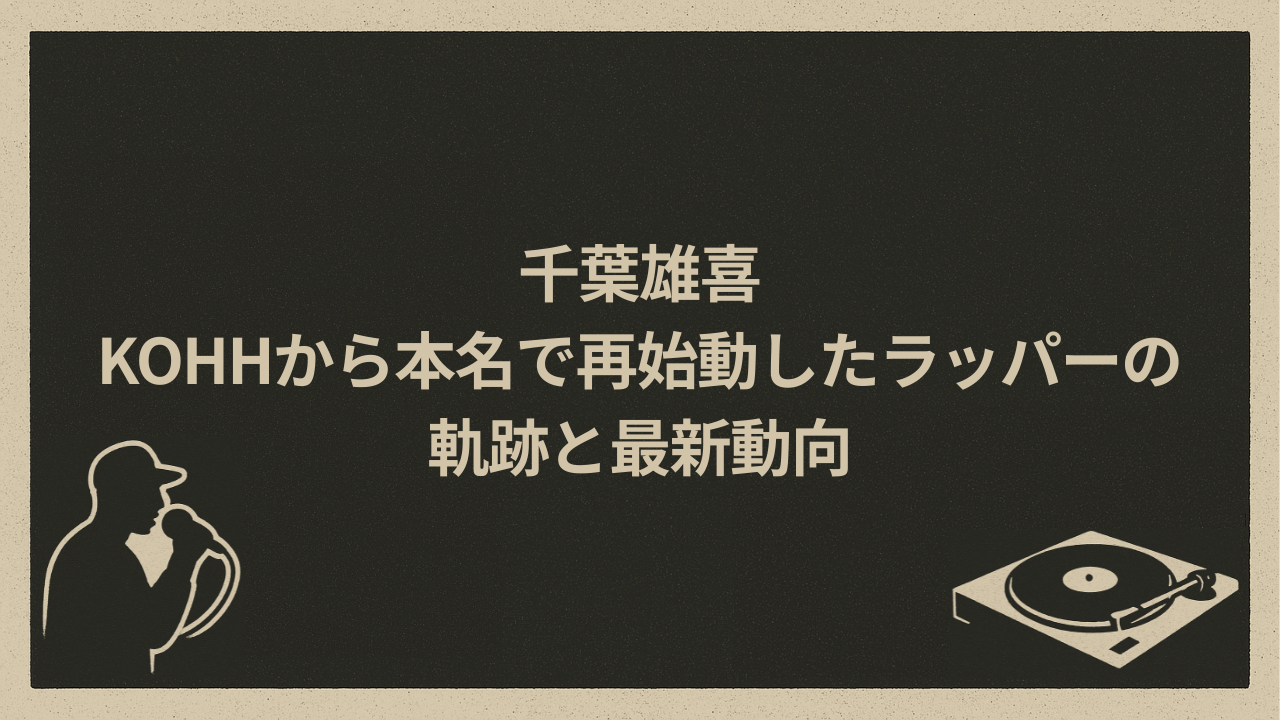




アーティストとしてのプロフィールと音楽スタイルを徹底解説-300x169.png)



