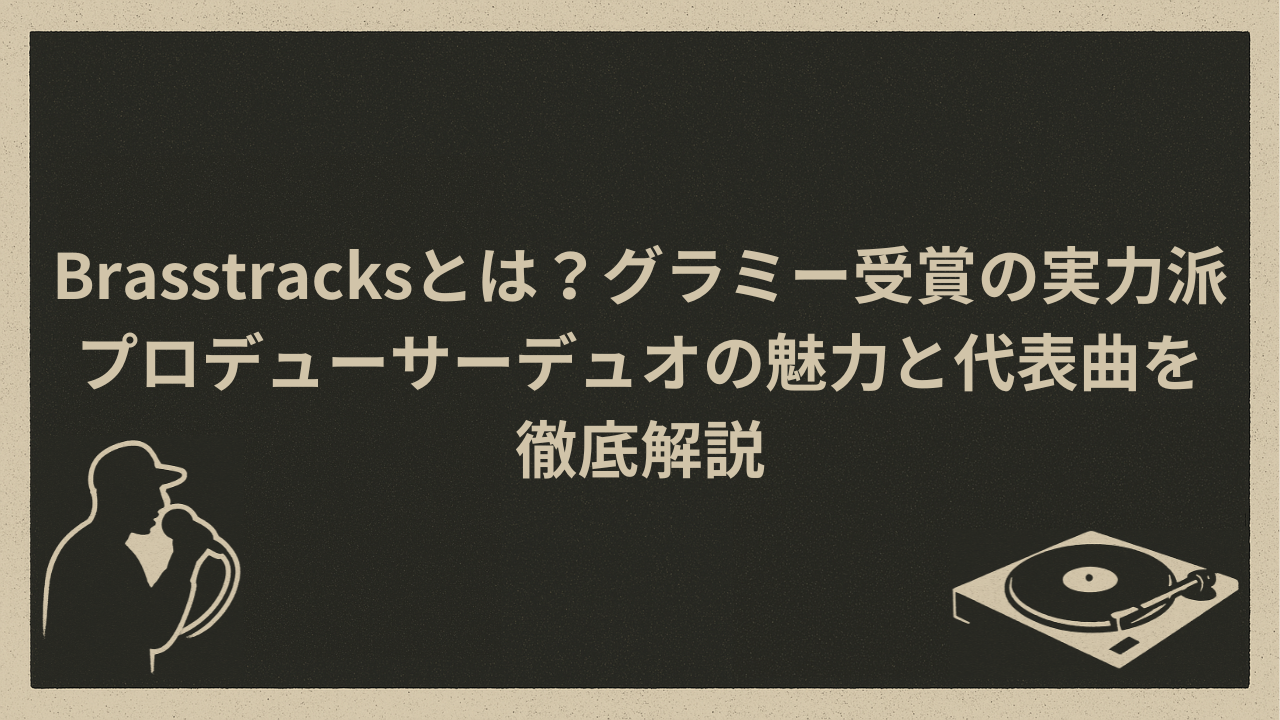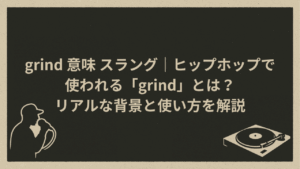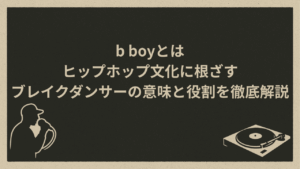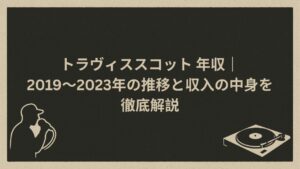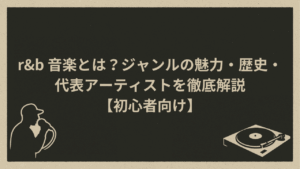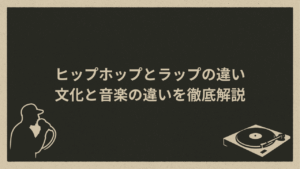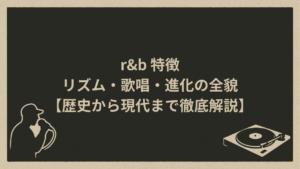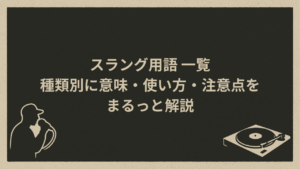Brasstracksとは?メンバーと結成の背景

Brasstracksとは何者?グラミー賞も受賞した実力派プロデューサーデュオ「Brasstracks(ブラスストラックス)」について、気になっている方に向けて徹底解説します。トランペットとドラムを軸に、ジャズ・ソウル・ヒップホップを融合させたサウンドは、Chance The RapperやAnderson .Paakとのコラボでも注目されました。本記事では、Brasstracksの経歴やサウンドの特徴、代表曲、人気アーティストとの関係、そして今後の活動までをわかりやすく紹介。初めて知る方にも、音楽ファンにも響く内容を意識して構成しています。検索上位の関連記事を比較し、より深く、正確な情報を盛り込んでいますので、Brasstracksに関する最新で信頼できる情報を知りたい方はぜひご一読ください。
メンバー紹介(Ivan JacksonとConor Rayne)
Brasstracks(ブラスストラックス)は、アメリカ・ニューヨークを拠点に活動する音楽プロデューサーデュオで、**トランペット担当のIvan Jackson(アイヴァン・ジャクソン)**と、**ドラム担当のConor Rayne(コナー・レイン)**によって構成されています。二人の音楽性はそれぞれ異なるジャンルに根差しつつも、驚くほど自然に交わり、ジャズとヒップホップ、R&Bを見事に融合させた独自のサウンドを作り上げています。
Ivanはトランペットの演奏だけでなく、作曲やプロデューススキルにも長けており、そのセンスは同業のアーティストからも高く評価されている人物です。一方のConorは、グルーヴ感あふれるドラミングと柔軟なリズム構成力で、ライブでも録音でも観客を惹きつけます。
音楽学校出身の背景と結成ストーリー
彼らが出会ったのは、音楽の名門校として知られるニューヨークのThe New School for Jazz and Contemporary Music。ジャズの理論や即興演奏を学ぶ中で、IvanとConorはお互いの音楽に対する情熱と感性に強く共鳴したと言われています。
在学中からセッションを重ねるうちに、「ジャズの技術とヒップホップのビートを融合したい」という共通のビジョンが芽生え、自然とユニットとしての活動が始まったそうです。彼らの名前“Brasstracks”は、「ブラス(ホーン)」と「トラック(ビート)」を掛け合わせたもので、そのまま音楽スタイルを端的に表現しています。
グラミー受賞歴とそのきっかけ
Brasstracksが一躍注目を集めたのは、2016年にリリースされたChance The Rapperの「No Problem」でのプロデュース参加。この楽曲が第59回グラミー賞で最優秀ラップ・パフォーマンス賞を受賞したことで、彼らの名前も一気に広まりました【引用元:https://hiphopdna.jp/features/10682】。
この受賞は、単なる偶然ではなく、彼らの音楽的挑戦が業界に新風を吹き込んだ結果だと語られています。特に「生楽器によるプロダクション」が評価される流れの中で、Brasstracksのアプローチは既存のヒップホップサウンドに対する一種のアンチテーゼとしても受け止められたようです。
今では、多くのアーティストたちが「Brasstracksと組んでみたい」と語るほど、ジャンル横断的なプロデューサーとしての信頼を築いています。
#Brasstracksの魅力 #グラミー受賞 #IvanJacksonとConorRayne #ジャズとヒップホップの融合 #ニューヨーク発の音楽デュオ
Brasstracksの音楽スタイルと特徴

ブラス×ビートの革新的な音作り
Brasstracksの音楽を一言で表すなら「ブラス(ホーン)とビートの融合」。一般的なヒップホップでは打ち込みやサンプルが中心になりがちですが、彼らは生のトランペットとドラムを前面に押し出すことで、音の「立体感」や「熱量」を生み出しています。
特にトランペットの主旋律がビートと絡む瞬間には、耳に心地よいスリルが走ります。デジタルに偏りがちな現代のプロダクションの中で、あえてアナログな要素を重視する姿勢が多くの音楽ファンに支持されている理由のひとつだと考えられています。
アイヴァン・ジャクソンの繊細かつエネルギッシュなトランペットと、コナー・レインのグルーヴィーなドラムがぶつかり合いながらも調和する――その音像は、他に似た存在が見当たらないほどユニークです。
ヒップホップ・ジャズ・R&Bの融合サウンド
Brasstracksの楽曲には、ジャンルの境界線を軽やかに飛び越える柔軟さがあります。ヒップホップのビート感をベースにしながらも、随所にジャズの即興性やR&Bのメロウな質感が織り込まれており、耳の肥えたリスナーにも刺さる作りです。
このジャンル横断的なアプローチが、多くのアーティストとのコラボレーションにつながっているとも言えるでしょう。Chance The RapperやAnderson .Paak、Khalidなど、時代を象徴するアーティストたちと共演してきた実績が、それを裏付けています【引用元:https://hiphopdna.jp/features/10682】。
「ジャズの技術力」と「ヒップホップの感性」を高い次元で融合させた彼らのスタイルは、ジャンルにとらわれず音楽を楽しみたいリスナーにとって、新鮮で刺激的な選択肢になっています。
ライブパフォーマンスの魅力と評価
Brasstracksの真骨頂ともいえるのがライブパフォーマンス。レコーディングされた音源ももちろん完成度が高いのですが、彼らの音楽は“生”でこそ真価を発揮します。
ステージ上では、アイヴァンのトランペットが情熱的に空気を震わせ、コナーのドラミングが観客の体を自然と揺らします。ライブ演奏における即興的なアレンジや、客席とのインタラクションも魅力のひとつ。音楽的スキルの高さと観客を巻き込むパワーが、世界中のフェスやクラブイベントで高く評価されています。
近年ではライブ映像のSNSシェアも増え、「一度は生で体感したいアーティスト」として認知されるようになってきました。
#Brasstracksの音楽性 #ブラスとビートの融合 #ジャンルレスなサウンド #生演奏の魅力 #ヒップホップとジャズの融合
代表曲と注目の楽曲リスト

「No Problem」(Chance The Rapper)への貢献
Brasstracksの名を一気に広めた楽曲といえば、やはり**Chance The Rapperの「No Problem」**でしょう。2016年にリリースされたこの楽曲は、第59回グラミー賞で最優秀ラップ・パフォーマンス賞を受賞しており、そのサウンドの根幹を支えていたのがBrasstracksの2人です。
トランペットによる軽快なフレーズとグルーヴィーなドラムが特徴的で、ヒップホップにブラスセクションを導入したスタイルが新鮮なインパクトを与えました。プロデューサーとしての彼らの実力が広く認識された瞬間でもあり、この曲がきっかけで様々なアーティストとのコラボレーションへとつながったと言われています【引用元:https://hiphopdna.jp/features/10682】。
「Golden Ticket」など自主作品の紹介
Brasstracksはコラボ作品だけでなく、自主リリースのアルバムやEPでも独自の音楽性を展開しています。特に注目されているのが2020年に発表された**『Golden Ticket』**というアルバムです。
この作品は彼らにとっての“通行証”であり、ジャンルの垣根を超えて自由に音楽を表現する場でもありました。収録曲にはMasego、Common、Duckwrthといった実力派アーティストが参加しており、ヒップホップ、ジャズ、ソウルが巧みに混ざり合っています。
「Golden Ticket」では、生楽器の温かみとビートの洗練がバランスよく共存しており、Brasstracksの集大成ともいえる一作に仕上がっています。
Spotify・YouTubeで人気のトラック分析
リスナーの反応を最もリアルに感じられるのが、SpotifyやYouTubeでの再生回数です。中でも人気なのが、「Say U Won’t」や「Improv #1」などのインストゥルメンタル楽曲。耳心地の良さと洗練されたメロディで、多くのプレイリストにも選ばれています。
また、ライブ映像がYouTubeにアップされると、コメント欄には「本当に生演奏!?」「ジャズとヒップホップの融合が新しい」といった声が多く寄せられており、動画プラットフォーム上でも彼らの音楽性が高く評価されていることがわかります。
SNSとの相性も良く、TikTokやInstagramで彼らのトラックがBGMとして使われる機会も増えており、Z世代からの注目度も着実に高まっているようです。
#Brasstracks代表曲 #NoProblemプロデュース #GoldenTicketアルバム #Spotify人気トラック #ライブ映像評価
コラボした有名アーティストたち

Anderson .Paak、Mac Millerなどとの共演
Brasstracksの名前が世界的に広まった背景には、実力派アーティストたちとの豪華な共演歴があります。特にAnderson .Paakとの共演では、互いの音楽性が自然に融合し、ジャズとソウルを基調としたサウンドにより深みが増しました。Paakの持つグルーヴ感とBrasstracksのライブ感あふれるブラスアレンジは、リスナーの心を一気に引き込む力があります。
また、故Mac Millerとのコラボレーションもファンの間では語り草です。Mac Millerの「Dunno」のアコースティックVer.では、Brasstracksがバックを務め、美しくも切ないサウンドで、彼の内面をそっと引き立てていました。こうした関係性は、単なる共演にとどまらず、音楽的な信頼の証でもあると言われています。【引用元:https://hiphopdna.jp/features/10682】
ボーカリスト・ラッパーとの多彩な連携
彼らの魅力は、ブラス編成にとどまらない柔軟性にあります。MasegoやDua Lipa、Rexx Life Rajなど、ジャンルやスタイルの異なるアーティストとのコラボも積極的に行っており、それぞれの楽曲にBrasstracksらしい“有機的なサウンド”を加えてきました。
ラップとの相性も抜群で、例えば「Before We Go」などではトラップビートにトランペットの音色が自然に溶け込み、ヒップホップの世界観を一段階引き上げるような印象を与えています。シンプルな打ち込みだけでは出せない、人の手による音のあたたかさが評価されている理由かもしれません。
プロデュースワークの幅広さと今後の期待
Brasstracksは演奏だけでなく、プロデューサーとしての活動の幅広さも注目されています。上述の「No Problem」以外にも、Chance The RapperやGoldLinkなどのプロジェクトに携わっており、トラックメイカーとしてのセンスにも定評があります。
今後はさらにR&Bやネオソウル系アーティストとのコラボが増える可能性もあると予測されており、グラミー受賞経験を持つ彼らだからこそできる“音楽の架け橋”が期待されています。ジャンルを超えて多くのアーティストが信頼を寄せる存在として、Brasstracksの名は今後ますます音楽シーンで不可欠なものになっていくでしょう。
#Brasstracksコラボ #AndersonPaak共演 #MacMillerとの絆 #多ジャンル連携 #プロデューサーとしての才能
Brasstracksのこれからとシーンへの影響

Z世代からの支持とSNSでの反響
Brasstracksは、Z世代からも高い支持を集めているユニットです。その理由の一つは、ブラスとビートという一見レトロな組み合わせを、現代的な感性で再構築していることにあります。特にTikTokやInstagramでのショート動画では、Brasstracksの楽曲がBGMとして使われることも増え、日常の中に溶け込むような存在になりつつあると評価されています。
また、彼らのライブ映像やセッション動画はYouTubeでも拡散されやすく、「リアルな演奏」に飢えている若いリスナーたちの心をつかんでいます。SNS時代においては、バズより“信頼性”が重要になってきているとも言われており、そうした意味でもBrasstracksの音楽性はZ世代の感性にフィットしているようです。【引用元:https://hiphopdna.jp/features/10682】
アンダーグラウンドからメインストリームへ
もともとはニューヨークのジャズシーンをルーツに持つBrasstracksですが、いまやアンダーグラウンドとメインストリームの架け橋のような存在となっています。ヒップホップ界隈での評価を得たのち、R&Bやネオソウル、さらにはポップスの分野にも活動の幅を広げており、グラミー受賞以降はより多くのメディアにも取り上げられるようになりました。
特に2020年代以降、ライブ演奏や生音を重視するアーティストが再び注目されており、Brasstracksのようなスタイルは今後さらに重宝されていく流れにあると言われています。「DTM世代」へのカウンターとしても、彼らの生演奏のエネルギーが評価されているのです。
今後のリリース・ライブ情報・ファンへのメッセージ
Brasstracksはこれまで定期的にEPやシングルをリリースしており、今後の新作も期待されています。SNSを通じて「制作中」と匂わせる投稿がされることもあり、ファンの間ではアルバムリリースを待ち望む声が高まっています。
ライブに関しても、アメリカ国内を中心に精力的にツアーを行っており、過去にはTiny Desk Concertsへの出演や大型フェスでのパフォーマンスも好評でした。今後のツアー情報や来日公演に関しては、公式SNSやYouTubeチャンネルなどをチェックしておくとよいでしょう。
最後に、彼らは常に「音楽でつながる楽しさ」を大切にしており、リスナーに向けて「音楽は感情を表現する手段であり、誰でもそれに関われる」といったメッセージを発信し続けています。音楽そのものの楽しさと奥深さを、これからもBrasstracksが届けてくれるはずです。
#Brasstracksの未来 #Z世代の音楽トレンド #メインストリーム進出 #ライブとSNSの融合 #音楽でつながる力